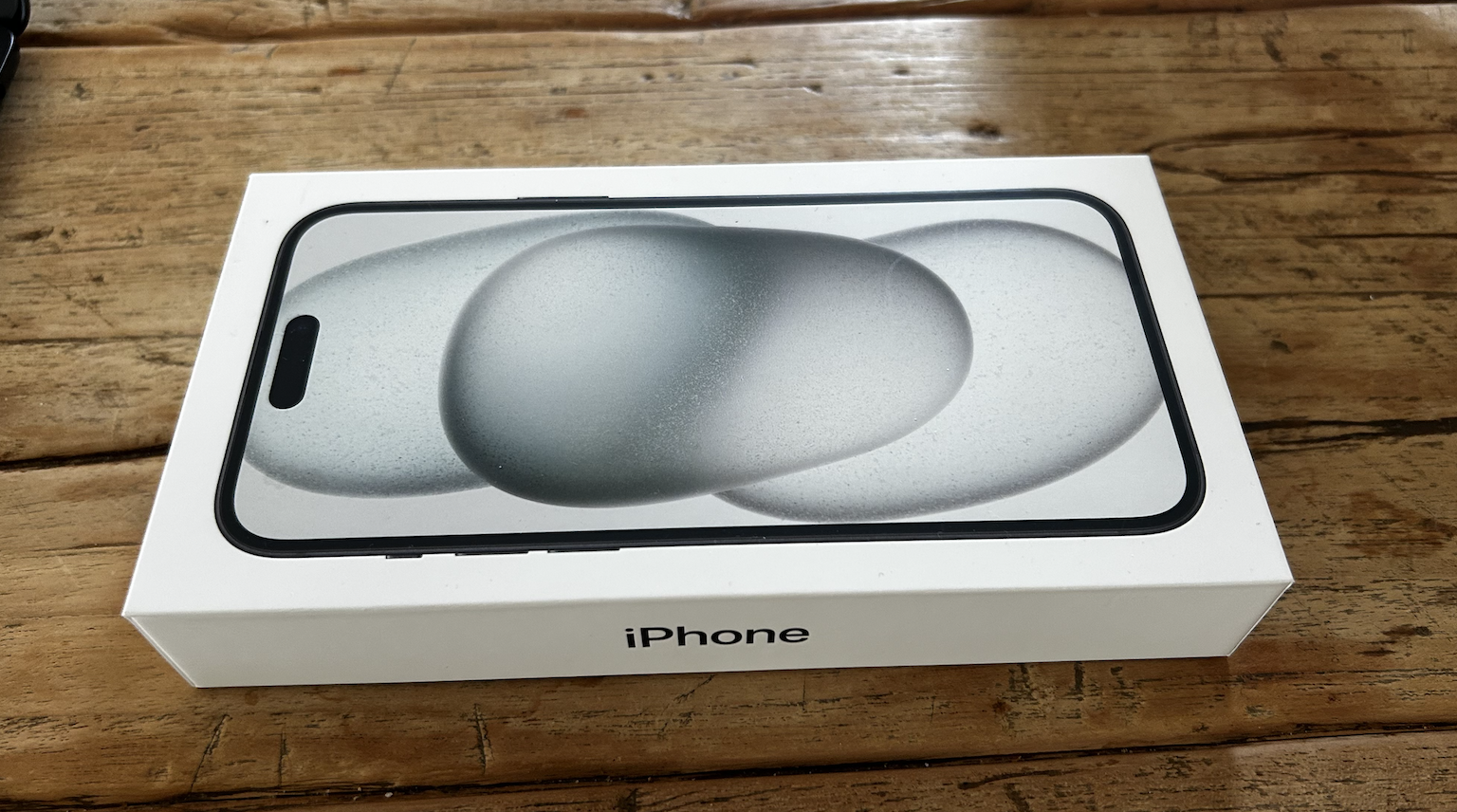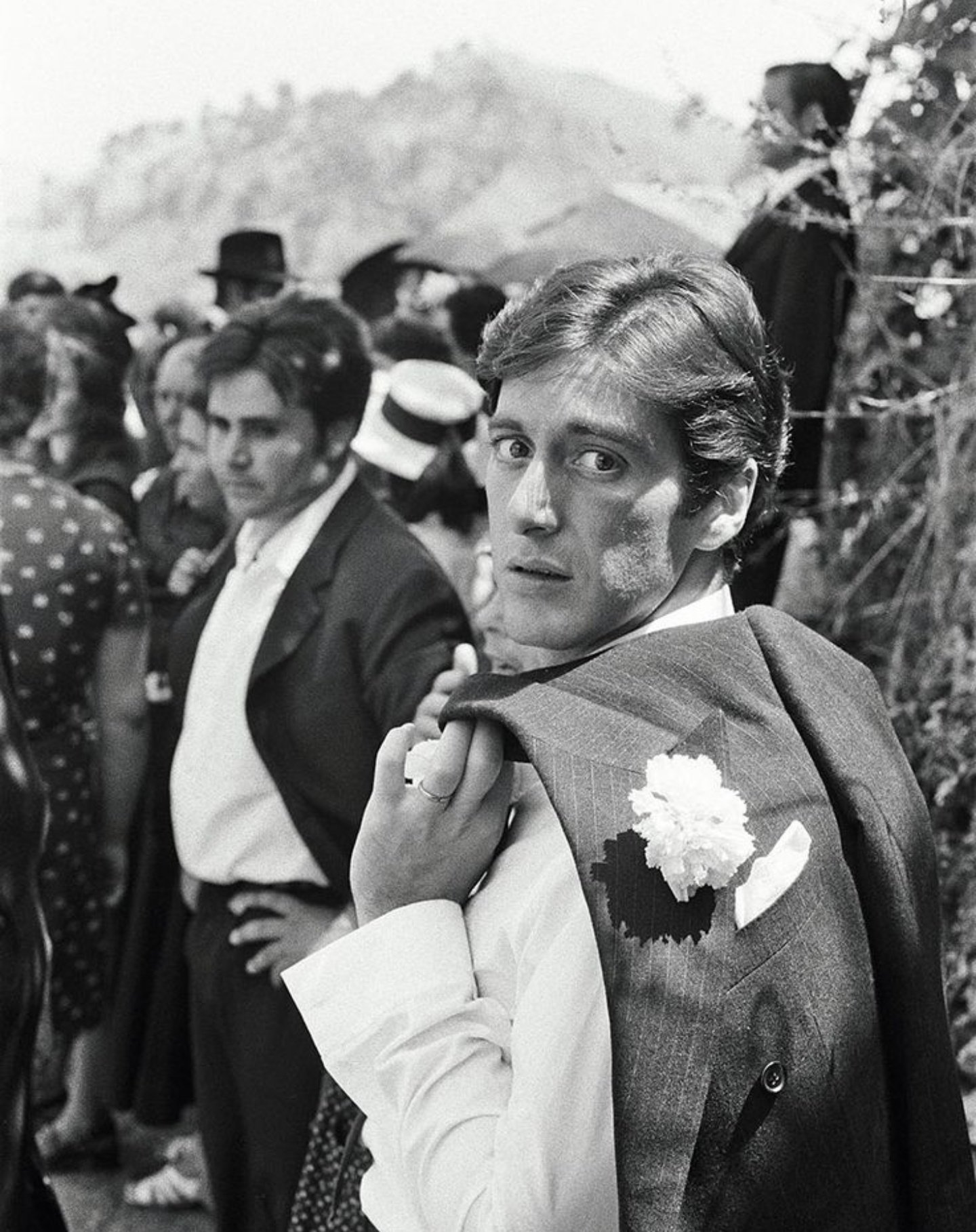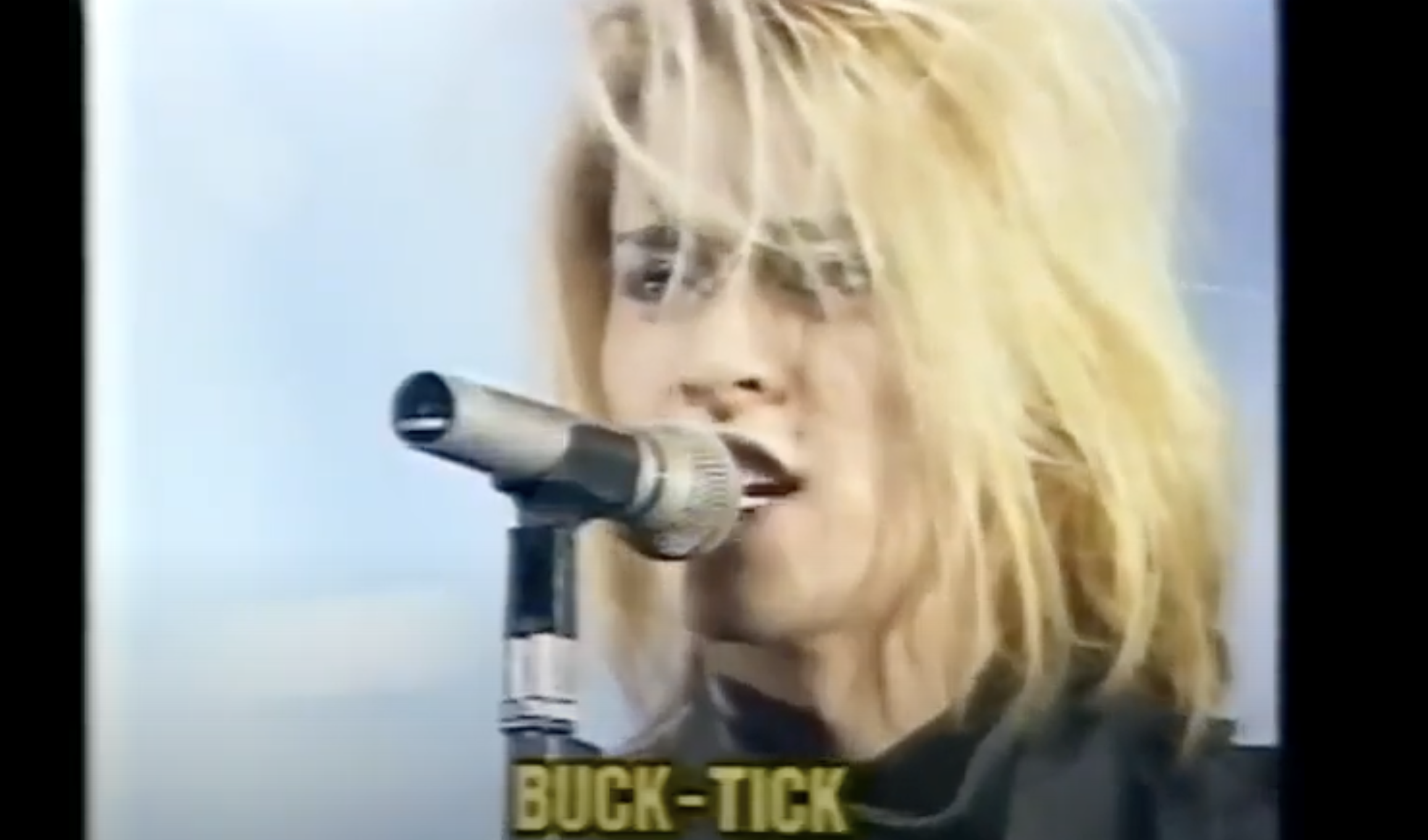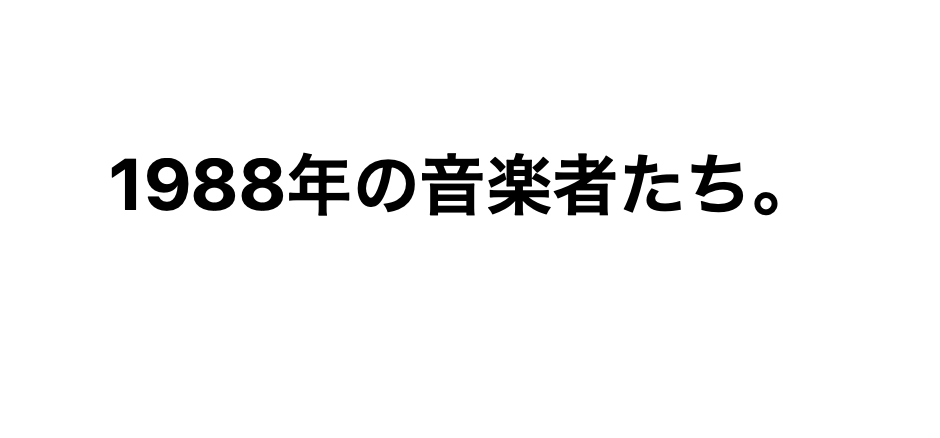イメトレで絶対に合格する二輪(バイク)免許教習の秘密。
二輪の免許は18時間で取得できますが、卒検まではあっという間です。
シミュレーションと学科で4時間もとられ、オートマ教習も1時間あるので、実質13時間。
たった13時間で、たいていが理論的に把握をすることなく、なんとなく上手くいって合格したり、補習を受けて時間をかけて合格したりします。
いきなりCB400SFという大きな塊に乗るので、みな緊張と恐怖でこけまくります。
「まずは行って、教官の教わる通りにやろう」と大抵の人が思いますが、それだと間に合いません。
事前に勉強し、イメトレしなくては、補習の連続となるはずです。
筆者自身、途中でそれに気づいてライディングの勉強とイメトレを開始しましたが、初日以前からやっていれば…と思うことがたびたびでした。
もしまだ教習所に通う前なら、絶対にこれを読んでイメトレをしていたほうがいいです。
筆者は高校1年の誕生日の週にすぐ原付免許をとり、ガソリンスタンドのバイトで貯めたお金でMTX50という原付としては大きなモトクロスバイクを買いました。
原付の免許は一日で取れますが、実習はスクーターに一瞬乗るだけ。
それでも怖かったのを覚えています。
ということは、ミッションのバイクを買った場合、いきなり公道というわけです。
二輪教習を受けていないのに、ミッションバイクを乗りこなさなくてはいけません。
不良は先輩から教われますが、自分には先輩でバイク乗りはいませんでした。
そうなると、Youtubeもインターネットもない時代、「本」に頼るしかありません。納車までの間(期間は覚えてません)、ひたすら部屋でイメトレです。
右手のスロットルを開けながら…クラッチを…。
そうして、家から数十キロも離れたバイク屋でバイクを受け取り、「ありがとうございましたー」と見送られながら、初のミッションバイクの運転を路上からするわけです。
しかし、イメトレを重ねた結果、緊張の発進もなんら問題なく、家までノーミスで帰ることができ、大きな自信になりました。
その後は、北海道じゅうの山の中に入っていっては野宿をするという高校生活。大好きだったバイクはそのまま東京までフェリーで運び4年ほど乗っていましたが、最後はバックパッカーの旅をして沖縄に辿りつき、クルマの免許をとってバイクは廃車になりました。
それ以来、バイクとは縁遠くなってしまいましたが、40歳ごろから友人と一緒に免許を取ろうということを話すようになったのにもかかわらず、ずるずると、5年も経ってしまいました。が、46歳になってこのままじゃいけないと、教習所に通いだしたというわけです。
教習初日のバイク体験は、まさに25年ぶり。
初日まで楽しみで仕方がないという感じでしたが、最初は「回転数を2000から3000くらいに上げて、クラッチを…」みたいな指導があり、一応いわれるままやってみましたが、多少ぎこちない。だって、回転数なんて気にして乗ったことないからです。結局「メーターみないで前を見て」と言われて、「だったらいつも通りやろう」ということで、懐かしの発進をスムーズに決めて「これだー」となりました。
全部からだが覚えていたのです。
そうして走り出すと、いろんなことを言われます。
「左のステップはクラッチレバーの上に出して!」
これは自分で乗ってきたクセなので、正直困りました。二速からニュートラルに入るの嫌ですよね。
「とまるときは二つ前くらいの線でクラッチを切って!」
そんなことまで指示されます。クラッチ切る場所なんてローギアかセカンドギアかで違うんだから、いちいち指定しないでほしいと思ったものです。
でも、教官の言うことは従おうと当然思ってますので、しっかり指示通りこなします。
外周もさっとスピードを出して、減速してというのを繰り返し、歓びを感じていると、一緒に始めた男の子ががくがく、うぉんうぉんやっています。
正直、いきなりこんなに走らせるってどうなの? という疑問しかありません。
教官は「イメトレは当然やってきてるよね」という態度です。
でも、たぶんその子はやってきてません。一方、もう一人の女の子は低速ながらしっかり走ってます。イメトレを確実にやっています。
そうして、50分はあっという間に経過し、男の子は補習となるのです。
この初回までにやっておくべきだったイメトレはなんなのかというと、「クラッチ切ってとまれ」です。
どんなバランス系のスポーツでもそうですが、止まり方を知らずにスピードは出せません。
止まり方に自信がないと、発進時にアクセルをまわすこともクラッチを繋げることも怖くてできません。なので、アクセルまわさずにクラッチひらいてがくがく、クラッチひらかないでアクセルまわしてぶおんぶおんになるのです。
はじめての発進は一速なので、普通はぐおんとスピードに乗せて、すぐにクラッチを切って、ゆっくりブレーキ(右手と右足を同時利用)で止まります。
スピードが落ちてエンジンが止まりそうなときも、とにかくクラッチを切ります。
「クラッチ切ってブレーキをすれば大丈夫です!」とはっきり言ってあげないと、あまりに可愛そう。
子どものころスキーを親から教わったときのこと。たしかにうちの親はスキーが得意。だから教え方がど下手でした。
止まり方をしっかり教えないので、とまれずに木に激突。少しスキーが嫌いになりました。その後独学で止まり方を研究し、スキーが大好きになりましたが、あの木にぶつかる感覚は一生忘れないし、恐怖感も忘れません。
初めてスクーターのアクセルを回したときの恐怖感もやっぱり覚えています。
とにかく、スピードが出るものは最初は怖いのです。
私は結局その後、バランス系にはまってウィンドサーフィン、サーフィンとやってきましたが、やはり最初のスピードは圧倒的に怖いです。
だからこそ、止まり方が大事なんです。
その上で発進です。発進は、アクセルをためらわずにゆっくり開ける、クラッチも同時にゆっくり開ける。それだけです。
どちらかをためらうと、ぐわんとなります。
もし左手をためらうと半クラで空回りして騒音になり、あまり進まないのでびっくりしてバランスを崩し、転倒します。
アクセル回してるのに! となるでしょう。
アクセルを回さないでクラッチをゆっくり話すと、教習車のCBは進むそうです。自分が乗っていたときのイメージだと、その場合はエンストという認識だったので驚きでした。パワーの差でしょうか。
実は、たいていのバイクはアイドリングでエンストせずに進みます。
そこからゆっくりスロットルを開ければエンストしません。
ただし、この走り方はいずれ覚えればいいことだと思います。
というわけで、初日までのイメトレは、
・右手と左手の同時開放(恐れずに)
・クラッチを掴んでブレーキ(エンストを防げる)
この二つだけです。
教習二時限目
教習所によってやることは違いますが、私が通っていた教習所では1日目が1-a、二日目が2-aです。
卒検とは違う小さなコースを走ります。この日から2速に変えたり、スラローム的なカーブ(S字よりも急)を走ったりします。
2速はクラッチを切って、左足つま先でギアをでローギアからセカンドにあげます。ニュートラルにならないようにしっかり上に上げます。
アクセルを少しあけて、クラッチはまだゆっくりめに開きます。発進ほどではありません。
3速以降はクラッチはすぐ離しても大丈夫(実際は2速も含めてすべて大丈夫)です。
「スピードにめりはりつけて!」と指示が飛びますが、この時点で生徒たちはスピードをあまりあげられません。
まだ恐怖感があります。
止まるときは2速3速の場合はクラッチを切らずにブレーキングを行い、とまる少し前でクラッチを切ります。エンジンブレーキも使えることが卒業の条件なので、はやいクラッチ切りはNGです。
しかし、1速ではブレーキより先にクラッチを切ります。
この辺が混乱を招くと思います。
この時間か、次の時間あたりから急角度カーブを走りはじめますが、カーブに入る前にしっかりフットブレーキで減速(自分でこれならいけると思うまで)します。
これを教官が指示しているのか、私には記憶にないです。
そして、ブレーキをかけつつ、向かう方向、行きたい方向を見ます。
教官からは、「どこどこの標識を見て」などといわれます。
これは、見た方向にバイクが曲がることと、その後のスロットル開度の設定のために必要なのですが、実際は目標が標識であるわけがなく、まずはブレーキングポイント、バイクを曲げるところを見ます。カーブの手前、バイクをまっすぐにする最後のところです。
その後、次のブレーキングポイントを見ます。
峡路ではある程度スピードがあるので、目線のほうへバイクが自然に曲がっていく感覚は掴めないと思います。
ただ、実際は見ているほうにセルフステアリングでバイクは倒れてハンドルが切れます。
そのままだと倒れてしまうので、スロットルを開けながらブレーキングポイントに向かいます。
曲がるときの順番
- ブレーキングポイントを見つめて、しっかりブレーキングする。
- 次のブレーキングポイントを見る。バイクが傾き曲がるので、スロットルを調整する。開けるとアウトに向かい、閉じるとインに向かう
- スロットルで調整しながら、バイクを起き上がらせていき、再びブレーキングする。
中型ではリーンウィズしか教えない?
と言われていますが、実際はさまざまなステアリングの技術が必要になってきます。
体とバイクの角度が一緒になるリーンウィズから、頭を残すリーンアウト、体をイン側に入れるリーンイン。
これは2日目あたりでしっかり頭に叩き込んで、理論武装しておいたほうがいいです。
二輪教習におけるリーンウィズ、リーンアウト、リーンインにはそれぞれ役割があります。
外周 リーンウィズ
スラローム リーンアウト
クランク、S字 リーンウィズ
外周はどんな方法でもいいのですが、基本はリーンウィズです。
なぜリーンウィズをするかというと、目線による曲がり方を実践するのがリーンウィズです。
正しい姿勢とタイミングによるリーンウィズは、教習所の外周さえ楽園にします。
楽しいリーンウィズのやり方をイメトレしましょう。
また、「最終的に結局全部リーンウィズでいいのだ」となるかもしれませんが、まずは教習所のやり方で見てみます。
まずスラロームのリーンアウトですが、バイクの傾きに関係なく頭を残すことで、自分が倒れません。
前に進む推進力があれば、すぐにバイクが立ちます。
ブレーキングして曲がりたいところでバイクを傾け、同時にスロットルを少し開けて推進力をつけてバイクを立ち上がらせ、少しフットブレーキをかけて膝荷重で反対方向に傾ける。の繰り返しです。
中型はこれで卒検まで行くのが無難です。教官がそう教えるからです。
ですが、実際はスラロームだと、目線移動だけで体の入力なしで行えます。その場合はリーンウィズになります。
リーンインは、白バイなどがやるのですが、バイクをあまり倒したくないけど曲がりたい場合に使われます。
バイクは右に曲がろうとすると、左に倒れるような遠心力が働くので、少し右に倒してバランスを取ります。
でも、白バイはキャリアが大きいので倒せません。
なので、人自身が重りのようにバイクの内側に出るのです。
その分、バイクはあまり倒さずに曲がれます。
クランク、S字は最初、このリーンインで曲がりやすくなるかもしれません。最終的には、目線移動だけのリーンウィズが有効です。
三時限目
おそらく、どの教習所でも、スラロームははじまっているはずです。リーンアウトですね。
スラロームは右に左にと移動しますが、スタート地点とゴール地点は同じです。
だから、ゴール地点方面を見て頭を残していいのです。
頭を残すのはバランスの問題なので、残したまま近くを見るのは問題ありません。
コツは2速で入り、
・右から左に曲がる場合、コーンの少し手前右あたりまでフットブレーキで減速する。
・タンクをニーで挟んで、右膝を左に入れるようにして車体を倒す。
・同時に曲がる方向にハンドルをしっかり向ける。
・倒れてバイクが曲がったら、アクセルをぶおんと一回開く。(がくん という挙動になります)
・再びフットブレーキで減速
の繰り返しです。
ニーでの倒しこみを意識しなくても、スピードが落ちていればハンドリングでも倒しこみができるはずです。ニーで挟むのは下半身をホールドすることで上半身がリラックスできるからです。
アクセルを開くのは、直立させるためです。スピード稼ぎのためではありません。教官は「これで時間がクリアできる」と言います。気にしないでください。私はしっかり聞き流しました。自分が安全に運転できる技術を身につけるためには、クリアタイムなんてどうでもいいのです。私は計ってもらったことはありません。
この、「アクセルを開いて直立させる」という行動は、バイクの基本中の基本です。
倒したあとに必ずスロットルを入れるのです。
入れないと倒れます。
この、「スロットルを入れれば倒れない」というバイクとライダーの信頼関係があって初めてバイクを倒せるのです。
次はシミュレーション。この時間を無駄に感じるかもしれませんが、たぶん、ゲームをやっている人には余裕です。
5時限目は私の教習所では一本橋がありました。
もしストレートで合格する場合、一本橋の適格な指導は受けられません。
教官は、ある程度うまくこなしている人には細かい指導はしません。
「クラッチゆらゆらしすぎだよ〜」「フットブレーキなんて使ってんじゃないよ」
と嫌味は言われます。
クラッチをゆらゆらしても、フットブレーキも使ってもいいのですが、それはまた後述します。
一本橋も、もっと事前に情報を仕入れておけば良かったと自分は後悔しています。
事前に情報を仕入れ、イメトレすべき内容とはこれです。
まず、一本橋の目標
「低速でまっすぐ走り、バランスを崩しても推進力とセルフステアリングで復帰する技術を得る」
です。
もの凄く当たり前のことですが、教官ははっきり教えてくれません。
私が最初に言われたのは、「ハンドルをふらふらさせて、まっすぐ前を見てやってみてください」でした。
振り返ってみると確かにそうなんですが、理論的にまったく理解できないまま、チャレンジすることになります。
低速になると、ハンドルはそもそもふらふらします。その状態でも「まっすぐ走り、なおかつ右に左に傾かず、傾いたとしても低速の安定した推進力で復帰する。その際はセルフステアリングを使う」
という練習です。
そのために、極低速半クラというのを一速で作り、同じペースで最後まで乗り切ります。
この半クラが上手くいけば、基本的にはバランスは崩さないのですが、人によります。
一段階のみきわめまで、オートマ教習を覗けばあと一時間。みきわめの前までに一本橋を完璧にする人はあまりいませんが、このイメトレをやればもしかしたらできるかもしれません。
ここで、他のテクニックなどを読んで迷わないために、注意事項を書いておきます。
・逆操舵による倒れ込み対策はしないこと(オススメしている人が多い)
・20秒や1分を競う白バイの平均台は違うテクニックなので気にしないこと
一定速度の進入と目線によるハンドル保持の仕方を理解すれば、落ちるほうが難しくなります。
うちは鬼の半クラで!
個人的な考えでいうと、低速はあくまで条件です。低速になるとバランスを取るのが難しいので、意図的にそのシチュエーションを作り出し、それでもハンドルをまっすぐに保つ技術を習得します。
一番優先すべきは目線です。
たとえばアイドリング走行を試してみると、顔の向き、つまり目線だけでバイクは次々と曲がります。
かなりの力でハンドルがくーっと動きます。
そして、顔の向きをまっすぐにすると、ハンドルはまた強い力でまっすぐになります。
このセルフステアリングの作用を使うために、目線、顔の向きだけでは絶対なのです。
免許も取得して公道に出ると半クラで走り続けるような機会は減りますが、たとえばフットブレーキで減速して一本橋のように走ってみるとします。
減速しても、ちょっとアクセルを入れることでバイクが立つというのを繰り返して、まっすぐ走れます。
身体の荷重やハンドル操作で傾いたバイクを復帰するのではなく、ハンドルを目標に向かってまっすぐにして、アクセルを入れることでバイクを直立させる。これは、「そうなのだ」とわかっていなければ、荷重やハンドル操作をしてしまうので、頭で理解するほうが先です。
ここまで、しっかり理論を叩き込めば、一段階みきわめはクリアできるはずです。
二段階の実習は6時間ですが、途中で回避やブレーキ体験といったものも入ってきます。
コースを覚えて(イメトレで)、「ウィンカー消し忘れた!」とやってるとあっという間に片方のコースは終わります。
うちの教習所では、aコースで2時間、回避などの体験で1時間(スラロームや急制動、一本橋含む)、最後にdという別コースで3時間です。
なので、コースを覚えるのと同時に一本橋やスラロームをやってると、いつの間にか終わってしまいます。
ミスがなければないで、不安のまま卒検を迎えることになります。
でも、理論武装していれば大丈夫です。
大型と中型の違い
それは、排気量ではありません。
いつでも練習できるか否かです。
すべてではありませんが、250ccや400ccのバイクを持っている場合は、課題の克服のために練習ができます。
しかし、バイクを持っていない中型(原付ミッションを持っている人は別)免許に挑戦している人は、教習中、外で練習が一切できません。
だからこそ、イメトレと理論武装しかありません。
予習しないで望むと、簡単に補習コースです。
大型はアイドリングのクラッチ開きでもちゃんと進むし、ちょっとスロットル開ければすぐ直立するし、中型よりイージーな面もあるのです。
中型でいろいろ慣れている分、各課題の取り組みに対して余裕を持って挑めますし、内容も知っているので、より深く探究できます。
一方中型は、基本的に初めてのことばかりです。
そして自由に練習ができない。しようと思っても、課題に追われてあっという間に卒検です。
大型で役に立つ教習所のテクニックは、中型では必要ない場合が多いです。たとえば、中型の一本橋で10秒を狙うと、本来の意図から外れてしまいます。
このブログに中型の体験を書き残そうと思ったのは、「初めてバイクに乗る人がストレートで合格した」という記事を読むたびに、「なんとなく合格してしまった」感が失礼ながら否めないからです。
大型での記録を残していても、中型でなんとなく過ごしてしまったことを忘れて、「中型のときにすべきだったこと」をあまり振り返らなくなるかもしれません。
バイクに乗るのがはじめてで、多少間違った理論構築だったとしても、自分なりの課題を作って各時間を過ごしたほうが絶対にいいです。中型には中型なりの初歩的な理論があります。そして、教官は議論相手にはなってくれません。
今回はこれを試してみよう。駄目だった、じゃあ次はこれで。という感じで記録に残していくことをオススメします。感覚で乗り切るのもありですが、しっかり把握していくほうが公道では安全です。
坂道発進、急制動、S字についてはほとんどふれていませんが、はっきり言えばそれほど難しい技術ではありません。
中型で難しいのは一本橋、クランク、90度カーブ、スラロームです。
そのための低速走行を実現するものとして半クラ、目線という感じです。
この記事を読んで中型免許に望めば、絶対に役に立ちます。
特に、目線とハンドル角度の関係についてはお役立ち度100パーセントです。
他の人は「目線が大事だから」しか言ってくれません。
「なんで大事なの?」と質問しても、気持ちのいい答えは返ってきません。
また、「ハンドルの舵角を得るためにさまざまなことをするのがバイクである」というのもこの記事の主旨です。でもバイクは感覚的になんとなく曲がるので、なんとなく卒業してしまいます。ほんとに何も考えなくても、リーンウィズでちゃんと曲がれます。
でも、「傾くとハンドルが切れる」ではなくて、「切りたいから傾ける」と思うことで、本来の主旨からぶれずに済みます。おそらく、そう思うことでカーブ進入時に積極的な前傾になるはずです。すると、とにかく楽しくなります。
中型免許はここに書いてあることを実践すれば、絶対に受かります。
でもなにより、卒検以上に得るものがあります。それを教習中に得ることができるのです。
おわり。
Similar Posts:
- 私はきれい? 醜い? 10代の女の子がyoutubeで問いかける現象
- 北朝鮮の米爆破プロパガンダビデオはゲーム「コール・オブ・デューティ」からの借用だった
- フィットネス動画を撮影中に列車に轢かれる。
- メキシコ麻薬カルテルのリーダー「エル・ロコ」逮捕へ
- 日本アニメのメイクで人気の娘を母親が擁護
- 3歳の子供がアイス・バケツ・チャレンジをして思わずFワード。
- Googleアプリはアップデート でもMapsは配信されず。
- DJデミオ、買って半年で新車に買い換えた。
- shironekoって何?
- ミステリー 1938年の携帯電話